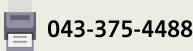cbaニュース
第279号 「「ケーブルテレビショー2007」初の土曜開催まずまずの船出」
[2007.07.03号]
6月の中旬は、毎年、ケーブルテレビショー関連のイベントで、昼も夜も大忙しになる。
6月15日、「ケーブルテレビショー2007」の分科会Ⅱ『革命的なメディア環境の変化の時代にケーブルテレビに期待される役割、可能性を探る」というパネルディスカッションでのモデレーターの仕事を無事終了し、NHK研修センターが来場者の休憩や情報交流のために毎年オープンしている「よいぼれラウンジ」で、ほっと一息。内容については、様々な意見があろうが、ともかく時間どおりに進行した。
最後のまとめで、パネリストの麻倉怜士先生は、「ケーブルテレビの帯域を活用して、スーパーハイビジョンに取り組むべき」と話した。NHKの技研公開でも、スーパーハイビジョンが注目されており、そう遠くない時期にスーパーハイビジョンの時代がやってくるのだろう。
「Web2.0でビジネスが変わる」「YouTube革命」「ウェブ3.0型社会」などの本を書かれているビデオジャーナリストの神田敏晶さんは、Web3.0の時代にも言及した。(詳しい内容は忘れてしまった。忘却の世代に入ったのだろうか。ご興味のある方は、7月24日に、新社会システム総合研究所〈SSK〉で、≪YouTube SNS Second Lifeの先に『Web3.0時代はこう変化する』)というテーマで講演がありますのでぜひ参加してみてください)
http://www.ssk21.co.jp/seminar/re_S_07228.html
さらに、TV3.0は、「こんな番組がみたいのではありませんか」と気を配ってくれるテレビになるのでは、と話した。小さな広告も数が集まれば、けっこうな収入になる。テレビやウェッブなどを使って、広告収入のアップが期待できるのでは、とも。
『「通信と放送』のこれからがわかる本』を書かれている情報通信総合研究所の櫻井康雄さんは、地域のエコ環境を重視したケーブルテレビの様々な事業展開に期待を寄せた。(櫻井さんは、その後、6月25日付けで人事異動の発令があり、7月2日から、NTTコミュニケーションズでu-Japan政策を担当することになった)
夕方からは、ケーブルテレビ関係者が情報交換をするメーリングリストである「よいぼれ」が、立ち上がってから今年でまる10年を迎えたことを記念して、東京ビックサイト近くの居酒屋で10周年の記念パーティー。
連日飲み過ぎていたので、2次会は行かずに早めに引き上げ、家に帰ると、ケーブルネットワーク千葉(JCN千葉)から、地上デジタル放送対応の工事のお知らせが入っていた。
とうとうやってきたか。2年前の今頃、地上デジタル放送への切替をお願いしようと電話をしたら、「まず理事会にご相談してください」とやんわり断られて、このマンションは、年齢層が高いので、最後の最後にならないと地上デジタル放送対応の改修をしないのではないかと半分あきらめていた。
しかし、そうはいっても、2005年12月には、Bフレッツ対応を行ったから、誰かNTT関係者が住んでいるのではないか、とも思っていた。2006年夏に、もうそろそろ光の時代か、ということで、NTTコムのADSLから光に変更した。あまり速くなったとは思わない。
おとといの6月30日午後4時過ぎ、工事の後にやってきたJCN千葉の営業マンと話をしていて、「速度チェック」をしてみると、19Mbpsということだった。営業マンは、「けっこう出てますね」という。「これで出ている方なの?」というと、「遅いところでは、2Mのところもありましたよ」という。
「ウチは、常時30Mが出ます」というが、「その昔、インターネットの申し込みをしたら、このマンションは対応できていないといわれた」というと、「デジタルになったので対応可能になった」という。
営業マンは、ケーブルプラス電話の説明も行った。ケーブルプラス電話が始まったのは知っていたが、インターネットができないのだから、このマンションでは、ケーブルプラス電話は利用できないのだろうと、5月の末に、ひかり電話に替えたところだった。ケーブルプラス電話もデジタルになったからできるようになったということだ。
<う~ん。知らなかった。マンション内部の動きにも注意を払っておかなければいけないな。といっても、光が来て、地デジがくれば、情報系のアクセスでこれ以上変わるということもないだろうが。あっ、あった。PLCだ。これもやがてやってくるのかも知れない>
何はさておき、いよいよアナログTVからデジタルTVライフへの乗り換えだ。7月1日から松下のHDD内蔵STBを導入するというからそれを早速に頼んだ。「私の担当では第1号です」という。順調に進めば、12月からはVODサービスも始まるという。
20数年前から、正確にいうと東生駒で行われたケーブルテレビの実験システム「Hi-OVIS」を見学して、VODを知ってから、早くこういう時代になってほしいものだと思ってきた。どうやら狼少年にならなくてすみそうだ。
しかし、少々不安になってきた。提供されるVODのコンテンツと筆者のコンテンツニーズは合致しているのだろうか、と。
なんだかんだといって、夜中にビールを飲みながら、見たいのは、何も考えずにすむスポーツやスポーツニュース。もうすぐ相撲が始まるが、大相撲ダイジェストを待っているのがつらい。グビグビ、とやりながらテレビのスイッチを入れて、すぐに見たいのだ。こういうニーズを満たすとなるとHDD内蔵STBに活躍してもらうことになるのかもしれない。
VODのコンテンツには、地元のコミチャンをぜひ入れてほしい。夜中になると、テレビショッピングが中心で、それらしいコミチャンを夜中にグビグビやりながらみたことはない。昼間、グビグビやりながらコミチャンをみているわけにもいかない。
JCNグループ局のコミチャンがあってもいい。小田原でいまどんな話題があるのか、などぜひ見てみたいものだ。
甲子園の高校野球の出場校の紹介ビデオが試合前に流されるが、全国の主要なケーブルテレビ局の自己紹介ビデオやわが町、あるいはわが町の名物、名所旧跡などの紹介ビデオなんかがあっても見てしまうかもしれない。
訪ねてみたい町、という印象を見るものに与えたら、それはそれですごい意味を持ってくる。観光事業への貢献だ。すぐに来なくても長い人生の間に一度くらい足を運ぶことだってあるだろう。
例えば、山口県が生んだ偉大な俳人種田山頭火の住んだ庵の紹介ビデオが流れて、最後に、山口市の金光酒造の同名のお酒「山頭火」のPRが流れたら、思わず注文しそうだ。
http://www.c-able.ne.jp/~sake-h/santouka.html
このお酒、本当においしい。取材帰り、新幹線に乗り込むときにKIOSKで山頭火のワンカップを6本買い、半分を友人の土産にしようと思った。しかし、飲み始めると、あまりにおいしいので名古屋を過ぎたあたりで、残り1本になってしまった。全部たいらげてしまおうかとも思ったが、このおいしいお酒はぜひ俳人種田山頭火の好きな友人にあげたいと、代わりに、タイミングよくやってみたワゴンサービスのお酒を2本買い込み、その最後の1本だけは泣く泣く友人の土産にした思い出がある。(い)
【フォトレポート巻頭記事】
「ケーブルテレビショー2007」初の土曜開催まずまずの船出
2007年6月14日(木)から16日(土)の3日間、東京・有明の東京ビックサイトにおいて、国内最大の業界イベントである「ケーブルテレビショー2007」が開催された。今回の目玉は、何といっても初の土曜日開催である。これまでの同イベントは、すべて平日開催で、主要なターゲットは全国各地から上京するケーブルテレビ事業者であった。池袋のサンシャインシティで同イベントを開催していた頃から、関係者の間では、土曜日に開催して、ケーブルテレビのプレゼンスを一般の人にも広く認知してほしい、という要望があった。しかし、開催日程は、ほぼ2年前には押さえられており、6月のこの時期に、土曜日を入れた木から土の3日間の日程を押さえることはできなかった。東京ビックサイトに会場を移してから、土曜日開催の要望はさらに高まり、今年、念願の土曜日開催が実現した。
来場者総数は、92,510名で、昨年比108.51%。木、金は、それぞれ昨年比122.24%、125.05%と来場者数が増加した。これは、平日の開催日が2日間になったことで、主要なターゲットである全国のケーブルテレビ事業者が、この2日間に集中したためと思われる。(出張3日目の土曜日はそれぞれにいろいろと使い道がある。金曜の夜からみんなあちこちに消えて行った)
それでも、木、金の夜にケーブルテレビの関係者で情報交換をして、「これは見ておいた方がいい」という情報を仕入れて、土曜の午前中に展示ブースを確認して帰るケーブルテレビ事業者のトップの方もいた。
土曜日の主要なターゲットは、一般の方である。どれだけ一般の来場者があるか、関係者は気もそぞろだった。
土曜日の来場者は、23,084名であったが、一般の方の占める割合は75.62%で、初めての土曜日開催としては、まあまあの成果ではなかろうか。地下鉄のポスターなどを始め、東京周辺のケーブルテレビ事業者を中心に、「ケーブルテレビショー2007」の開催をPRした結果であろう。イベント会場の子供たちのくったくのない顔をみていると、あれこれ数が多いとか少ないとかいうのは、まあいいんじゃないの、という気持ちになってくる。そうはいっても、多い方がいいに決まってはいるが。
そして、一般の方は、子供連れが多く、ソフトウエアゾーンは、混雑時の駅の雑踏を思わせた。アダルトコーナーを横目に子供に手を引かれて、着ぐるみを追いかけているお父さんもいた。
NHK研修センターのラウンジで耳にした話では、アダルトコーナーの一角では、美女3人とジャン卓を囲んでマージャンを行い、美女が負けると服を脱いでいくというお遊びも行われていたそうで、勝利のガッツポーズのパフォーマンスで、回りのオーディエンスの拍手喝采を浴び、「癒し」の空間を満喫していた方がいたそうだ。
土曜日の来場者に占めるケーブルテレビ事業者の割合は、11.38%と前2日間に比較して落ち込んでいるが、ケーブルテレビ事業者を待つ会場のハードウエアゾーンの出展者からは、お客さんが来なくて暇で暇でしかたがない、という声が聞こえ、一方、会場を回るケーブルテレビ事業者の何人かからは、前日、前々日に聞いてみようと思ったけど、人がいっぱいで聞けなかったことが、聞けた。十分に説明してもらったので、納得ができた、という声も聞こえた。
あるブースでは、某ケーブルテレビ局の社長が名刺を出して、そのSTBをちょっと数台実験で使ってみたいと申し出ると、説明員が、血相を変えて、「わかりました。今、上のものを呼んでまいりますから、ちょっとお待ちください」と駆け出す光景にもぶつかった。
ハードウエアゾーンの出展者は、ケーブルテレビ事業者に来てもらいたいわけで、来年の土曜日開催に向けて、関係者の間で、創意工夫が行われ、改善の方向に向かうことを期待したい。
すでにいくつか耳に入った意見の一つに、土曜日に来る一般の方はハードを見にくるわけではないから、思い切って、土曜日のハードウエアゾーンは閉じてしまう、という意見があったが、そうはいっても、土曜日にゆっくりみたいケーブルテレビ事業者だっている。まあ、さしあたって、スタッフの陣容を減らすということも考えられるだろう。
●「バーチャルケーブルテレビショー2008(ハードウエアゾーン編)」の提案
筆者が、考えたのは、次のようなことだ。
ケーブルテレビ事業者といっても、全国のケーブルテレビ事業者が全員、しかも技術の方が、有明のビックサイトに来ているわけではない。
来てみたくても、仕事の関係で、どうしても現場を離れられないみなさんもいる。
そういったみなさんにメッセージを送る「バーチャルケーブルテレビショー2008(ハードウエアゾーン編)」を開催したら、いかがだろうか。
出展者の展示内容を3分くらいで、説明するビデオを撮影する。それをケーブルテレビ連盟なり、CATV技術協会なり、あるいは独自にサイトを開いて、イベント終了後、1ヶ月くらい、全国のケーブルテレビ事業者が動画で視聴できるようにする。これだけ、動画配信の時代になっているのだから、それくらいのことは手間を惜しまなければできるだろう。
その撮影に土曜日をあてれば、少なくとも「暇」ではなくなる。
どれだけのアクセスがあるのか、ということは保証の限りではないが、少なくとも、変化の激しい業界の技術動向を知りたい、と思うケーブルテレビ局の技術関係者は多いだろう。もっといえば、ケーブルテレビショーに来た人たちだって、見落としや忘れてしまうことだってあるだろう。そういうとき、「バーチャルケーブルテレビショー2008(ハードウエアゾーン編)」にアクセスすれば、確認でき、しかもわからないこと、疑問点は、担当者にメールするというコミュニケーションの広がりも期待できるだろう。
ソフトウエアゾーンに関しては、背景に写るキャラクターなどの著作権がうるさいだろうし、連日人だかりだから、とりあえず、バーチャルを利用しなくても問題はないだろう。今年の出展にあったかどうかわからないが、各社の営業担当者は、時間を見つけて、ゴルフスイングのチェックをする方が先だろう。
●「全国主要ケーブルテレビ局の自己紹介ビデオの集合サイト」の提案
さらにいえば、全国のケーブルテレビ局が自社あるいは自分の町を紹介する(両方でもいい)3分から5分の動画映像をサイトに載せてしまうのもできるのではないだろうか。そろそろ、夏の甲子園が始まるが、試合前に出場校の紹介ビデオを流している。あれと同様な感覚で、自社あるいは自分の町を紹介するビデオをサイトにあげ、6月のケーブルテレビショーの期間中と終了後1ヶ月くらい(常時、あるいは季節ごとにでもかまわないが)全国からアクセスできるようにする。
(どちらかというと社長はビデオに出ない方がいい。今後10年を担う中堅社員がいい。その方が、一般の視聴者には何となく好感を持っていただけるだろう。例えば、視聴者を50代後半と想定すると、自分の娘、息子くらいの感覚が何となく距離感が縮む。)
とりあえず、YouTubeの「ケーブルテレビ局とケーブルテレビのある町紹介版」だ。いきなり、一般にも開放するとシステムの問題が起こったりするといけないので、とりあえず、ケーブルテレビ業界内で互いにみて、あれがいい、これがいい、と意見を出し合うのも必要だろう。
そのプロセスを経て、一般にも開放すれば、わが町のケーブルテレビ局あるいはわが町がどのように紹介されているか、アクセスして視聴する一般の方も出て来るだろう。もちろん、誘導する仕掛けも必要だが、来年の6月のケーブルテレビショーにあわせれば、相乗効果も期待できるのではないだろうか。200局くらいが並ぶと壮観だと思うのだが。
ケーブルテレビショーの会場で、ケーブルテレビ富山のビデオレター投稿システム「eまちBOX」を体験して、『ケーブルテレビ局の自己紹介ビデオが集合したサイト』が必要ではないのかなと思った。ケーブルテレビ連盟のサイトから各局のサイトに飛べるが、サイトだから仕方がないが、人の姿はあまり感じられない。
何か人間味を前面に打ち出した局の自己紹介ビデオがあり、その町の今の名物、季節の話題などを短く2、3分で紹介していると、けっこうな「ケーブルアーカイブス」になるのではないかな、と思う。
今号は、「ケーブルテレビショー2007」のフォトレポート。途中で、デジカメのバッテリーがなくなり、一部の紹介になってしまいましたが、ご容赦ください。(伊澤 偉行)
| 次号へ | cbaニュース一覧 | 前号へ |